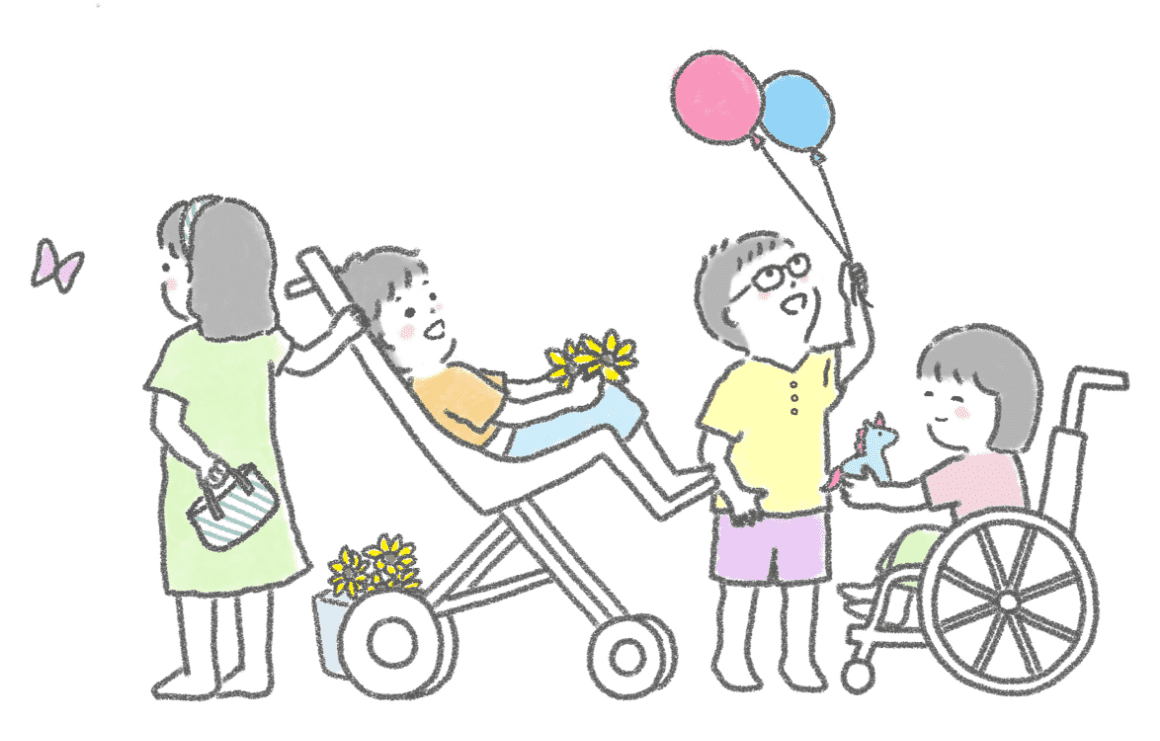医療的ケア児者支援
2025.10.25
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2025102400119 (10月24日付の信毎に掲載された記事)
~相談支援専門員としての独り言~
『受け入れを終了』という言葉だけをとると、マイナスなイメージが先行するかもしれない。
けれど、私はご利用者様やご家族にとって必ずしもマイナスになることばかりではないと思う。
障害児福祉計画では、児童発達支援センターの設置、重心児者を支援する放デイ・児発の設置が成果目標として掲げられている。
慢性的な人材不足という課題を抱える中、事業所が増えれば、さらに人材確保は困難になる。だからといって新たな社会資源をつくるのはやめましょうということではない。需要と供給に応じた地域のデザインを一緒に考えるためことが必要なのだろう。
高水福祉会は圏域の障害福祉サービスのトップシェアを抱える法人として、人口減少の中で持続可能な社会資源として在り続けるための策を考え続けている。多機能事業所(放デイ・児童発達・生活介護)が終了しても、法人として医療的ケア児の支援を撤退するわけではない。
地域全体で持続可能な体制構築をしましょうよというメッセージなんだろうなぁ。
医療・行政・福祉・教育が一丸となって、今回の方針を受け止め、地域課題を解決する策を本気で考えることが出来たとしたら、きっとご利用者様やご家族にとってプラスになる変化も出てくるはずだと、私は思う。
~以下、記事の内容~
「医療的ケア児者」の受け入れ2029年度で終了 専門人材の確保難しく 中野市の重症心身障害者施設
中野市笠原の重症心身障害者向け通所施設「かすたねっと」が、たんの吸引や人工呼吸など日常的な介助が必要な「医療的ケア児者」の受け入れを2029年度で終える方針を固めた。医療的ケア児者らに放課後等デイサービス(放課後デイ)や生活介護などを提供する北信地域(中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村)の拠点施設だが、看護師など専門人材の確保が難しいためとしている。
■看護師6人中4人が他施設と兼務
だが、高水福祉会は北信地域で入所、通所施設など計10カ所を運営。かすたねっとに勤める看護師6人のうち4人は他の施設との兼務で態勢は十分ではない。高水福祉会全体では看護師が11人いるが、正規5人のうち4人が29年度以降の数年間で定年退職を迎える見通しとなっている。
管理責任者など、看護師以外に配置が義務付けられる専門人材も限られている。こうした事情を踏まえ、かすたねっとの担当者は「法人全体で業務の効率化や集約を行い、限られた専門職や支援員らで持続可能な体制に再編していく必要がある」と説明する。
■しぐさや表情読み取り多岐にわたるケア
例えば気管切開を受けた医療的ケア児者へのケアは、酸素管理やてんかん発作への対応、胃ろうなど多岐にわたる。医師は常駐しておらず、会話が十分にできないケア児者のしぐさや表情から体調を読み取り、適時適切に対応する必要がある。こうしたケアの難しさも人材確保が進まない一因という。
高水福祉会は、看護師の定年を段階的に60歳から70歳に引き上げるなど人員確保や維持に努めてきた。だが医療・介護人材の不足は全国的な課題。かすたねっとの担当者は「できれば医療的ケア児者の受け入れを続けたいが現実的には難しい」としている。
■転居や転職の不安抱える人も
北信地域の医療的ケア児者の受け皿は限られている。家族には、受け入れ先が遠くなれば転居や転職を強いられるのではないかと不安を抱える人も。地域全体でケア児者を支える仕組みが求められる。
退職か、転居か、転校か―。次女幸歌(さちか)さんがかすたねっとの放課後デイなどを利用している飯山市常盤の田中慶子さんは途方に暮れる。幸歌さんは先天性染色体異常症の「18トリソミー」。気管切開に伴うたんの吸引や24時間の酸素管理などが必要だ。
幸歌さんは県飯山養護学校(飯山市)の小学部6年で、平日は午前9時~午後3時ごろまで同校で過ごし、その後、かすたねっとの車でかすたねっとへ移動する。田中さんは送迎に合わせ、時間を調整しながら同校でフルタイム勤務している。午後6時半ごろまでに幸歌さんを迎えに行き、一緒に帰る日々だ。
■選択の結果なら良いが...
現在は自宅と勤務先、幸歌さんの登校先、放課後デイの受け入れ先が比較的近いことが育児と仕事の両立を支えている。受け入れ先が遠くなれば、自身か夫の働き方を変えざるを得ない。変えたとしても夏休みなどの長期休み中の対応は難しい。
「選択の結果として子どもと家で過ごすなら良い。でも選択肢がなくて、自分が望む働き方を諦めざるを得ないのは違うのではないか」と田中さん。保護者が働いている間にケア児者が自宅以外で安心して過ごせることが難しくなる現状に疑問を投げかける。
■新たな受け皿を検討方針
医療的ケア児者や家族の生活を支援する県医療的ケア児等支援センター(松本市)は、かすたねっと以外がケア児者を受け入れたとしても人材難などの壁にぶつかる懸念は残る―と指摘。ケアが必要な人を医療機関などで日中に預かる「医療型特定短期入所」を含め、受け皿の在り方を探っていく必要があるとする。
高水福祉会は北信地域6市町村などでつくる障害福祉自立支援協議会の事務局も務める。今後は協議会を中心に新たな受け皿についての検討を進める方針といい、担当者は「ケア児者を継続的に支える態勢を地域としてどう構築していくか考えたい」としている。(宮沢久記)